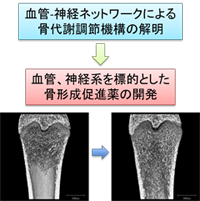科学研究費助成事業
科学研究費(科研費)とは

科学研究費とは、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、文部科学省及び日本学術振興会が取り扱っています。
関連リンク
初等・中等教育家庭科における「だし教育コンテンツ」の開発と活用
福留奈美准教授の研究課題「初等・中等教育家庭科における『だし教育コンテンツ』の開発と活用」が2020年に採択されました。概要は以下の通りです。※教員の役職は採択時のもの。(2023年度より教授)
研究期間
2020年4月1日~2025年3月31日
審査区分
小区分09040:教科教育学および初等中等教育学関連
研究種目
基盤研究(C)
概要
「だし」は和食文化を特徴づける重要なキーコンテンツのひとつです。小学校家庭科では、これまでも5年生のみそ汁を作る調理実習でだしを取ることをしてきましたが、新しい学習指導要領(平成29年告示)では「和食の基本となるだしの役割」が明記され、「だし」をどう教えるかが問われることになりました。しかし、だしの取扱いに関する教師研修の機会も教材研究のための情報蓄積も不十分な現状があります。そこで、本研究では、だし教育のためのさまざまな教育コンテンツ(たとえば教材として使いやすい図表や各種データ、動画、ワークシート、活動アイデアなど)を開発し、現場教師の意見を反映して改良を加え、だし教育コンテンツのモデルとして情報公開し提案することを目指しています。
真空包装による野菜の調味効果と組織構造との関連性および新規利用法について
熊谷美智世准教授の研究課題「真空包装による野菜の調味効果と組織構造との関連性および新規利用法について」が2022年に採択されました。概要は以下の通りです。
研究期間
2022年4月1日~2025年3月31日
審査区分
小区分08030:家政学および生活科学関連
研究種目
若手研究
概要
真空包装とは包装材に食品などを入れて包装内部を吸引脱気して密封する方法です。保存を目的に行われるほか、加熱をともなう真空調理にも用いられています。真空調理の特徴の一つとして味がよくしみ込むといわれていることから、真空包装後と加熱後に分けて調味料濃度を調べたところ、真空包装後においては常圧包装後よりも有意に味がつくことがわかりました。野菜に調味するためには加熱などにより細胞膜機能を消失させる必要がありますが、真空包装ではその必要がないことから、生の状態の食感を失うことなく調味可能であると考えられます。そこで、本研究では真空包装による調味の現象を種々の野菜について調べ、そのメカニズムを解明するとともに、新たな調理法としての活用法を検討します。
筋・血液を介した身体活動誘発性miRNAががんの発症やがん患者の余命に与える影響
膳法浩史講師の研究課題「筋・血液を介した身体活動誘発性miRNAががんの発症やがん患者の余命に与える影響」が2022年に採択されました。概要は以下の通りです。※教員の役職は採択時のもの。(2023年度より准教授)
研究期間
2022年4月1日~2025年3月31日
審査区分
小区分59040:栄養学および健康科学関連
研究種目
基盤研究(C)
概要
運動をはじめとする習慣な身体活動が「がん」を予防することは知られていますが、そのメカニズムについては不明なままです。本研究は、ヒトの体内で作られているマイクロRNA(miRNA)という分子に注目し、日本人における身体活動誘発性miRNAががんに与える影響を検討します。「なぜ、身体活動ががんに効果的なのか?」を明らかにできれば、国民に対する更なる運動の推奨と、運動を模擬した創薬の開発が期待されます。
超音波動画像と筋電図と嚥下音を用いた非侵襲計測による嚥下評価のための装置開発研究
谷本守正教授の研究課題「超音波動画像と筋電図と嚥下音を用いた非侵襲計測による嚥下評価のための装置開発研究」(研究代表者:鈴木裕東洋大学准教授)が2022年に採択されました。概要は以下の通りです。
研究期間
2022年4月1日~2025年3月31日
審査区分
小区分90130:医用システム関連
研究種目
基盤研究(B)
概要
超高齢者社会を迎える日本において、高齢者の死因第1位は肺炎であり、その多くが誤嚥性肺炎に起因します。しかし現状、嚥下機能を非侵襲(身体に負担をかけない)で 計測できるシステムは存在せず、検査は患者様の負担が大きいものです。そこで本研究では嚥下超音波動画像と嚥下音と頸部筋電図の3種信号を同時採取し各種解析・手法で嚥下能力の計測装置の研究開発を行い次代の医療機器としての実現を目指します。この実現のためには、以下ABCの各研究班の深いつながりとお互いのフィードバックにより実施されます。 A:超音波動画像、嚥下音、筋電図同時計測による非侵襲嚥下評価システムの開発研究 B:実験用嚥下評価用食材の開発、誤嚥防止フードデザインへの考察 C:新しい評価法の臨床評価と各種嚥下評価法の有効性の考察 私は主にB研究班の遂行に励み、高齢になってもいつまでも美味しいものを食べられる食品の開発につなげます。
瞬発系・持久系トップアスリートに特徴的な遺伝子多型・変異の同定と機能解析
膳法浩史講師の研究課題「瞬発系・持久系トップアスリートに特徴的な遺伝子多型・変異の同定と機能解析」(研究代表者:福典之順天堂大学先任准教授)が2022年に採択されました。概要は以下の通りです。※教員の役職は採択時のもの。(2023年度より准教授)
研究期間
2022年4月1日~2026年3月31日
審査区分
小区分59020:スポーツ科学関連
研究種目
基盤研究(B)
概要
ヒトの体力には大きな個人差があり、遺伝と環境の両方が関与しています。環境的要因としては、トレーニングや栄養などの影響がわかっていますが、遺伝的要因についてはよくわかっていません。双子研究や親子研究によると、筋力の個人差は遺伝と環境が約50%ずつ関与しているようです。
本研究は、具体的にどのような遺伝子がその個人差に関与しているかを明らかにします。本研究では、①トップアスリートの瞬発系・持久系運動能力に関連する遺伝配列の違い(遺伝子多型・変異)を同定し、②その遺伝子多型・変異によって調節される遺伝子の機能的役割を明らかにします。
期間終了等の科学研究費助成事業
膳法浩史講師の研究課題「スポーツ傷害(靱帯損傷・筋損傷・疲労骨折)を規定する機能的遺伝子多型の解明」(研究代表者:福典之順天堂大学准教授)が平成30年に採択されました。概要は以下の通りです。
研究期間
2018年4月1日~2022年3月31日
審査区分
小区分59020:スポーツ科学関連
研究種目
基盤研究(B)(一般)
概要
スポーツ傷害は競技力に対して単にマイナスに影響するだけでなく、時として選手生命さえも脅かすことがあります。スポーツ傷害の予知として遺伝子情報が活用できるのではないかと考えています。具体的には、競技アスリートを対象として靱帯損傷、筋損傷、疲労骨折といったスポーツ傷害に関連する遺伝要因について、全ゲノムDNAを対象とした網羅的遺伝子多型解析という手法を用いて明らかにします。共同研究者と協力することで既に二千人を超えるアスリートのDNAを得ています。スポーツ傷害に関連する遺伝子とその機能を解明することで、個人対応型のスポーツ傷害予防法の開発に貢献することを最終目標としています。私の担当は遺伝子解析であり、今後更なる発展を遂げるビックデータ解析に対応できるようにしています。
大田原美保教授の研究課題「米飯類の冷蔵による食味低下を視覚的かつ定量的に示す品質評価法の構築とその応用」が2019年に採択されました。概要は以下の通りです。
研究期間
2019年4月1日~2022年3月31日
審査区分
小区分08030:家政学および生活科学関連
研究種目
若手研究
概要
炊飯直後の米飯は透明感があり、程よい硬さと粘りを持ち美味しいものですが、保存のために冷蔵すると外観や食感の変化が生じて食味が低下してしまいます。食品産業界において、食味低下を客観的に捉える評価法の確立と炊飯後の品質制御は重要な課題です。我々は冷蔵によって米飯の透明性が低下する現象に着目し、厚さ0.1mmに機器で圧縮した米飯粒の顕微鏡観察を行い、その画像解析で捉えた変化から食味低下を視覚的・定量的に捉える新しい手法(以下、圧縮米飯粒法)を検討してきました。本手法は現在、白飯以外の飯への適用条件を検討して汎用性を高める段階にあります。本研究では、外観、味、物性が異なる米飯の圧縮米飯粒法のデータを蓄積し、官能評価や客観的測定値との相関関係を総合的に分析して、様々な米飯類の冷蔵による食味低下を視覚的かつ定量的に示す品質評価法の構築を目指しています。
膳法浩史講師の研究課題「日本人高齢者における骨格筋量と筋血流量の関連」が平成30年に採択されました。概要は以下の通りです。
研究期間
2018年4月1日~2021年3月31日
審査区分
小区分59040:栄養学及び健康科学関連
研究種目
若手研究
概要
加齢に伴う筋量と筋力の減少(サルコペニア)について研究を行っています。我が国はどの国も経験したことのない超高齢社会の国であり、15年後には3人に1人が高齢者であると推計されています。世界中が日本の高齢化対策の動向に注目しています。この研究では、いかに高齢者が自立して健康なままで生活できるかを目標に活動しています。そのためにメカニズムが不明であるサルコペニアを解明することで高齢者の自立した生活を支援できるのではないかと考えています。具体的には、高齢者において血流量の減少がサルコペニアに関係しているのではと仮説を立てており、そのデータを蓄積していきます。本研究では、血流を測定するために超音波エコーを利用しています。
福田亨准教授の研究課題「臨床応用を目指した骨組織における神経-血管機能の解明」が平成28年に採択されました。概要は以下の通りです。
研究期間
2016年4月1日~2019年3月31日
研究分野
整形外科学
研究種目
基盤研究(C)(一般)
概要
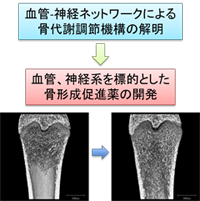
近年の高齢化社会の進展に伴い、急増する骨関連疾患を克服するため、医療応用につながる骨代謝調節の分子機構の解明を目的に研究を行っています。
我々はこれまでに、骨内の感覚神経が骨量を正常に維持するために重要であることを見出しました。そこで本研究では、神経による骨代謝調節の分子メカニズムの解明を試みています。これまでに神経に関連する細胞で、特定の分子を機能欠損させると骨量が変化することを見出しています。今後は関連する分子の機能解明し、複雑な骨代謝調節機構の解明を目指しています。
1) Fukuda et al. Sema3A regulates bone-mass accrual through sensory innervations. Nature 2013 497:490-493
藤島廣二客員教授の研究課題「インド経済圏内の食品流通システムの展開方向と日本農産物の輸出可能性の究明」(研究代表者:河合明宣放送大学教授)が平成27年に採択されました。概要は以下の通りです。
研究期間
2015年4月1日~2019年3月31日
研究分野
経営・経済農学
研究種目
基盤研究(B)(海外学術調査)
概要
インド経済圏(インド、ネパール、ブータン)は現在、経済発展途上にあり、急速な発展が期待されていますが、同経済圏内の食品流通システムは謂わば「ブラックボックス」状態にあり、その実態や問題点については未だに解明がほとんど行われていません。そのため、同流通システムの今後の変化の方向が不明確であるばかりか、政府等が採るべき改善策等も十分に明らかにされているとは言い難い状態です。また、日本などの諸外国にとっては、インド経済圏への食品輸出方策を確立するための情報が大幅に不足していると言わざるを得ません。
そこで、本科学研究費補助事業では既存データの収集・分析に加えて、現地の研究者との協力の下、ヒアリング調査やアンケート調査等により実態を正確に把握すると共に、これまでに取り組んできた中国経済圏の研究成果等も参考にしつつ、インド経済圏の食品流通システムの展開方向等の解明を試みています。
矢島克彦助教の研究課題「エネルギー代謝と生体リズムに影響を与える脂肪酸の解明」が平成29年に採択されました。研究概要、進捗状況は以下の通りです。
研究期間
2017年04月01日~2020年03月31日
研究分野
応用健康科学
研究種目
若手研究(B)
概要
栄養学領域からのアプローチによって睡眠を含む生体リズムの制御、そして健康増進に貢献する知見を得ることが本研究の目的です。我々は、動物のサーカディアンリズムの調節には食事の中でも、摂取する脂肪酸の”質” が関与すると仮説を立てています。仮設実証のため、ヒトを対象とし脂肪酸組成を変化させた食事摂取後のエネルギー代謝、睡眠時脳波、時計遺伝子発現および深部体温を全て同一の実験で評価する、国内・外で初の研究を試みます。摂取する脂肪酸の組成は、長鎖飽和脂肪酸と長鎖一価不飽和脂肪酸との比較から開始し中鎖脂肪酸、長鎖多価不飽和脂肪酸を含めた検討へと進展させていく予定です。生体リズムの乱れは睡眠の質悪化に繋がり様々な疾患を起こす要因となるため、本研究によって生活習慣病のリスク低減に有効な脂肪摂取のエビデンスを確立したいと考えています。
矢島克彦助教の研究課題「飽和脂肪酸、または一価不飽和脂肪酸の摂取がエネルギー代謝と睡眠構造に与える影響」が平成27年に採択されました。研究概要は以下の通りです。
研究期間
2015年4月1日~2017年3月31日
研究分野
応用健康科学
研究種目
若手研究(B)
概要
栄養素代謝と生体リズムは、多くの分子内機構を共有しています。栄養学領域からのアプローチによって生体リズムを制御することが可能となれば、現代人の健康維持・増進に大きく貢献できると考えられます。本研究はその第一段階として、異なる脂肪酸の摂取がエネルギー代謝、および生体リズムに与える影響を検討しています。
橋場浩子教授の研究課題「おいしい煮物を作るための呈味成分の食材中への拡散に関する研究」が平成23年に採択されました。概要は以下の通りです。
研究期間
2011年度~2013年度
研究分野
食生活学
研究種目
基盤研究(C)(一般)
概要
今までフィックの拡散係数Dは一定とされてきましたが、濃度依存するDがいくつか報告されており、二元拡散収着理論で解析することができました。本理論により得られた、3種のじゃがいも中のNaClの拡散パラメーターは、ペクチン含量と共に直線的に減少し、NaClの吸着座席はペクチンを含む領域にある事が示唆されました。また、3種の魚すり身中のNaClの同パラメーターは、荷電アミノ酸含量と共に直線的に増大し、NaClの吸着座席は同アミノ酸を含む領域にある事が示唆されました。これらの結果より、炭水化物食材、タンパク質食材いずれの場合も、そのラングミュアー型吸着座席は食材中の荷電部分であると推測されます。
二国間交流事業共同研究
二国間交流事業とは
二国間交流事業は、諸外国のアカデミーや学術研究会議との間で協定や覚書を締結し、我が国と当該国との間で多様な学術の国際交流を推進していく事業です。交流の主たる形態には、小規模グループ又は個人の研究者を対象とする共同研究、セミナー及び研究者交流(派遣・受入)があり、日本学術振興会が取り扱っています。
本事業では、個々の研究者交流を発展させた二国間の研究チームの持続的ネットワーク形成を目指し、我が国の大学等の優れた研究者(若手研究者を含む)が相手国の研究者と協力して行う共同研究・セミナーの実施に要する経費が支援されています。
関連リンク
独立行政法人日本学術振興会が実施する二国間交流事業共同研究として藤島廣二客員教授の
「高効率青果物流通システムの構築に関する日中両国間比較研究(中国との共同研究:CASS)」が平成26年に採択されました。研究概要は以下の通りです。
研究期間
2014年4月1日~2016年12月31日
概要


中国は21世紀に入ってからこれまでの世界に例がないほどの急速な経済発展を遂げ、今や日本を抜いて、アメリカに次ぐ世界第2位の経済大国になっています。しかし、国内の食品流通システムを見ると、様々な問題が少なくありません。その中でも特に大きな問題は、青果物流通の場合、輸送や貯蔵等の流通段階において約3割に達するといわれるロスが発生することです。本二国間交流事業では、こうしたロスの発生を抑える方法等を流通システムの側面から究明することを主要な課題としています。
平成27年6月に藤島客員教授、神田健策弘前大学名誉教授の2名が中国杭州大学にて、中国の流通システムの改善に資することを目的に、日本の卸売市場流通システムと農協共同出荷システムに関する講演を行いました(写真参照)。また、平成27年度並びに26年度の研究成果を本学「紀要(第8号)」に投稿し、9論文の掲載を得ました。なお、平成28年度は最終年度にあたるため、日本、中国両国でワークショップを行いました。